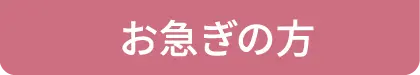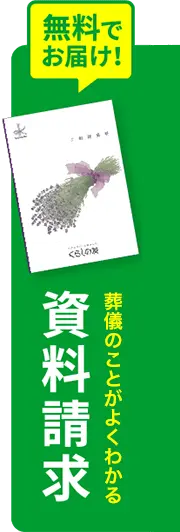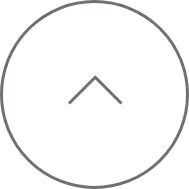"葬儀"の検索結果:9件
キーワードから探す
-
一般的な解釈では、通夜と葬儀にかかった葬儀費用、食事費用、それと読経、戒名は経費にできます。
葬儀費用は相続税の控除や保険の対象ですので、必ず領収書をもらって保管しておいてください。
また、香典には税金はかかりませんが、後日に行う香典返しの費用や法事等の費用は経費の対象外です。
-
斎場見学の際には、以下のポイントをご確認ください。
1.式場の広さ
2.お清め所の広さ
3.受付等の使い勝手
4.控え室の広さ・設備・使いやすさ(バリアフリー設計か、宿泊室はあるか等)
5.斎場全体の雰囲気(清潔感等)
6.斎場職員の態度、言葉づかい等
パンフレットやチラシではわからない部分を直接見て、確かめることができるので、興味のある方は積極的に参加されるとよいでしょう。 また、くらしの友でも定期的に斎場イベントを行っています。お気軽にご参加ください。
-
ご自宅で執り行う「ペット葬」を承ります。
お身体を清め、末期の水やお焼香など、真摯な気持ちで飼い主様に寄り添い、心あたたまるお見送りをお手伝いします。
1日プラン、2日間プランがございます。
-
いざという時のために事前に準備しておくとよいものを参考までにご紹介いたします。
1.遺影に使用したい写真
プリント写真であれば表面が絹目でなく、顔が10円玉以上の大きさの写真がよいでしょう。
また、デジタルカメラで撮影したデータでも大丈夫です。
2.お寺(菩提寺)の連絡先
3.親戚等や友人など、参列してほしい方々の連絡先
4.(互助会会員であれば)会員証
-
車両関係(霊柩車・バス・ハイヤー)や火葬場関係の方に心づけをお渡しする慣習が現在も残っているところもあります。
しかし、本来はお気持ちで差し上げるもので、こうした慣習も徐々になくなりつつあります。
※公営の火葬場はほとんど心づけを渡す必要はありません。
また、葬儀のお手伝いをしてもらった方へも、お世話になった度合いや関係などに応じて心づけをお渡しします。
自分より目上の方へお渡しする場合も、表書きを「志」や「お食事代」としてお渡しすれば失礼はありません。
受け取る方が負担に感じない額(3,000~5,000円程度)を目安に包みます。
もし心づけを辞退された場合は、後日品物をお渡しするなどで感謝の気持ちを伝えるのがよいでしょう。
-
まずは、ご遺族にお聞きすることです。「お別れを(弔問・会葬)をさせていただきたいのですが、お伺いしてもよろしいでしょうか?」とご遺族のご意向を伺ってみてください。
-
故人様の遺志やご家族の意向で、ごく近しい人だけで葬儀をすませた可能性も考えられます。
その場合は後日ご自宅に訪問してお香典をお渡しすることがかえって、ご家族の負担になることも考慮にいれたほうがよいでしょう。
四十九日の法要の際に線香や生花を送る、手紙にお悔やみのことばを書いて送るなどの方法でも十分に気持ちを伝えることはできます。
-
ご参列の方は会場に着くまで、宗旨などはわからないことが多いので、あまりこだわらなくても良いでしょう。
「浄土真宗では往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)とされ、『御霊前』の表書きは使わないとも言われますが、一般的には「御霊前」で問題ありません。
気になる方は「御香典」が無難でしょう。
-
仏式の葬儀の場合、四十九日前なら「御香典」か「御霊前」が多く使われ、四十九日の後(忌明け後)は「御仏前」というように使い分けるのが一般的です。
ただし浄土真宗の葬儀で持参する香典の表書きは「御霊前」は使わないので、「御仏前」とするのがよいでしょう。「御香典」は、仏教であればどの宗派でも使用可能な表書きです。